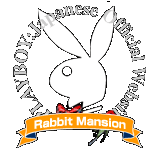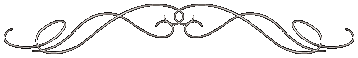
-PBインタビュー・コレクション-
ノーマン・メイラー
「命を捧げるほどの理想がない国は、戦争などするべきではない」
青木冨貴子=インタビュア
Interview by Fukiko Aoki
| まさに戦争の世紀として記憶されようとしている20世紀の終わり、アメリカはまたしても正義の戦争を戦った。20世紀に世界を支配した「戦う国家、アメリカ」の面目躍如たるところだが、21世紀を目前にして、この国の歴史を冷徹に見通せる知性とはいったい誰なのか? われわれはアメリカを代表する作家、ノーマン・メイラーに白羽の矢を立てた。25歳で華々しいデビューを飾って以来、'60年代には行動派の作家としてときにスキャンダラスに一世を風靡し、常に第一線で時代や文化にコミットしてきた興味深い人物である。すでに76歳になった作家は、この時代と世界をどう見ているのか。インタビューを申し込んでから、半年後の去る6月末、ついに『PLAYBOY』日本版の独占インタビューに応じてくれることになった。 |
|
●
|
 |
|
●
|
| ノーマン・メイラーは、紀元2000年に差しかかろうという現在、世界と時代 を語ることのできる数少ない作家のひとりである。最近、彼は『ワシントンポスト』紙に寄稿したコラムでコソボ紛争について記し、「オルブライト国務長官も、コーエン国防長官も、そしてクリントン大統領も、ミロシェビッチに対抗できるものではない。そのうちの誰もが戦争従軍経験がないからだ」と書き、戦争従軍体験のない政治家が戦争を始めたこ とを批判した。メイラー自身は1944年1月、米陸軍に招集され、第2次世界大戦の太平洋戦 線へと送られた。その時の従軍体験をもとに『裸者と死者』を発表。25歳で世界的ベストセラーを出した。'60年代には、コラムニストのジミー・ブレズリンとともにニューヨーク市長選に出馬するなど社会活動にも関わり、以来30冊以上の著 書をもつ。現在マサチューセッツ州ケープコッドの自宅で6番目の夫人ノリスさんと暮らし、執筆活動に専念している。インタビュー嫌いでも知られるメイラーを自宅に訪ねた。 |
| <青木(以下A)>第2次世界大戦の経験から聞きたいのですが、戦争が終了した時にはフィリピンにいて、その後日本に上陸したのですね。どこに上陸したのですか? <ノーマン・メイラー(以下M)>あのときは千葉の館山に上陸した。フジヤマが向かいに聳えていたよ。あの半島のことはよく覚えている。本当に美しかった。それから銚子と小名浜にも駐留した。 <A>館山にはどれくらい駐留したのですか? <M>しばらくいたね。3カ月くらいだ。あそこは僕にとって特別の意味がある。(終戦直前に米軍の)日本本土上陸作戦が計画された時、僕らは館山飛行場に上 陸することになっていた。なんとも賢明な米軍はこの日本軍飛行場を敢えて選んだのさ。ふたつの大きな崖が滑走路の両側を取り囲む格好でそそり立っている。上陸して歩き回ってみると、その崖(の側面)にはこんなに深い砲床が作られていて、滑走路に向かって照準を合わせていたんだ。もし、攻め込んでいたら、修羅場と化していただろう。われわれは本土上陸第一陣だったから、ほとんど全滅していたに違いない。だから、僕にとってヒロシマへの原爆投下は二重の意味がある。誰もが感じるように、原爆は信じられないくらいひどいことだった。しかし、原爆が投下されず、米軍の日本本土上陸作戦が開始されていたら、たぶん僕は死んでいただろう。 <A>『裸者と死者』も生まれなかったわけですね。実際、上陸したのはいつだったのですか? <M>戦艦ミズーリでの降伏文書調印後、第1日目のことだった。あの調印式のときには実に貴重なことを学んだよ。僕らは東京湾に停泊する何百という船のひとつに乗っていた。どんよりした雲が広がるなか、僕ら兵士全員はデッキに出て、調印式を生中継するラジオ放送を聞いていた。「いまやマッカーサー将軍は平和条約に署名するため、前方に進み出ました。まさにこの時、雲を破って太陽が東京湾上に輝いたのです」。もちろん、これはテレビ以前の時代だったからね。実のところ、現場はずっと曇っていた。その瞬間、僕は天啓のように計り知れない認識に目を覚ました。権力というものは、いつも嘘をつくということを目の当たりにしたのだ(笑)。それからというもの、僕は“偉大な人物の声明”など決して信用しない。 |
20世紀のトップニュースはヒロシマとホロコースト
| <A>ワシントンにあるジャーナリストのシンクタンク、ニュージーアムが先日、今世紀のニューストップ100を発表しました。第1位に選ばれたのが、米軍の広島、長崎への原爆投下、第2位はアメリカ人宇宙飛行士ニール・アームストロ
ング船長が初めて月面を歩いたこと、第3位は日本軍の真珠湾攻撃、ホロコーストは第7位です。この結果をどう思いますか? <M>そう、ヒロシマは生きているものすべてに重大なショックを与えた。『ホワイト・ニグロ』というエッセイでも書いたことだが、原爆のことを考えると、(あれだけの大虐殺では)ひとりの人間の死がまったく人目を引かず、注目されないことを悟る。考えてごらん、誰にも特に重要な意味もなく死ぬんだ。大災難で死亡するということは。多くの人々は、もし死んだら、少なくとも数人の目に留まって欲しいと願うものだろう。しかし、ヒロシマは予告なしの絶滅だった し、深遠なまでの心霊的ショックだった。 <A>その通りです。 <M>だから、ヒロシマはホロコーストと同列ではあるけれど、もっと不意で、もっと突然で、もっと無条件だった。 <A>米国では第2次世界大戦終結50年を記念する年に、ワシントンのスミソニアン協会が「原爆展」を企画したところ、アメリカ在郷軍人会や右翼団体の猛烈な反対にあい、事実上中止に追い込まれました。広島、長崎は多くのアメリカ人にとって、まるでトラウマのように残っているのでしょうか? <M>トラウマかどうか知らないが、たぶん、世界でもっともパワフルなこの国 で、アメリカ人は自分自身の間違いや国家の過失を無視するという不愉快な資質 をもっているのだ。われわれがしたことはモラル上、絶対的に間違っていたと発 言する者は誰ひとりいない。そんなことをすれば、政治家は政治的致命傷を負うことになる。まあ、どこの国でも同じようなものだろうが、ここではもっとはっきりしている。だから、アメリカ人は直視したくないことには、目をそむけてしまう。 <A>中国系アメリカ人の作家、アイリッシュ・チャンの記した『レイプ・オブ・ナンキン』という本が2年前に出版されベストセラーになりました。なぜこのような本がアメリカ人に人気を呼んだのでしょうか?あるいは、アメリカ人は広島の贖罪のための格好の手段として、これを利用しているのでしょうか? <M>まさにその通り。アメリカ人にはヒロシマに関して深い罪の意識がある。われわれはそれについてもう考えたくないし、問題にもしたくない。だから、日本 人が1937年に南京で中国人にひどいことをしたと耳にすると、ほっと安堵するのだ。 <A>だから、『レイプ・オ・ナンキン』がベストセラーになったと? <M>その本がなぜ、ベストセラーになったかなんて聞かないで欲しいよ。多くの作家と同様、僕の本がよく売れる年もあるし、売れない年もある。予想した以上に売れる年もある。でも、なぜなのか僕自身まったくわからない。それにしても、これまでに南京虐殺なんて聞いたこともなかったね。少なくとも、この50年 間は。それがいま、突然、話題になったというんだね? <A>そうです。まったく突然。 <M>まあ、日本に対する敵意というのは確かにある。いや、それ以上のものかもしれない。多くの人は反日的なものを見たいのかもしれない。アメリカ人のなかには、次の世紀はアジアが支配するのではないかという恐怖感が確かに隠されているからだ。 <A>これだけアジアと日本の経済が低迷してもですか? <M>10年前にはもっと強かっただろうがね。日本の景気後退以降、いまではあまり聞かなくなった。しかし、現在でも確かに残っていると思う。もし、日本と中国が手を結べば、米国とヨーロッパを簡単に蹴落としてしまうだろう。彼らの知性と献身、勤勉、それに人生への期待感が低いこと等がアメリカ人にとってつねに恐怖であり、不安材料なのだ。それに彼らの宗教はわれわれとかけ離れているから……。 <A>生活環境も文化もあまりに違っていて理解できない……。 <M>そう、すべてあまりに違っている。そこで、あの本がなぜ、人気になったのか。その解答を出そうとすれば、あの本のなかでアジアは決して美しく描かれていないからだ、といえるだろう。『レイプ・オブ・ナンキン』に登場する中国人はよいイメージではないし、日本人はもちろんのことひどいものだ。そこで「見てみろ、われわれはなかなかよくやっているではないか。アジアであのふたつの国がやっていることを見てごらん」ということになるのだろう。 |
戦う国家、アメリカというセルフイメージ
| <A>'67年の『PLAYBOY』インタビューで、「米国はこの地球上のどの国より、戦う国家というセルフイメー
ジをもっている。だから心理的にベトナムから脱出できないのだ」と発言していますね。それは今回のコソボ空爆でも、同じなのでしょうか? <M>あれは歴史の皮肉とでもいうべきものだろう。もし、クリントンが大統領でなかったら、「地上軍を送ろう」と即座に決定したことだろう。しかし、クリントンはそうできなかった。コラムニストのジミー・ブレズリンが面白いコラムを書いている。彼が早朝5時にソーホーを歩いていたら、モニカ・ルインスキーを見かけたというのだ。そこで彼はこう自問する。「あの娘は(コソボの)戦争を始めたのが自分だということを知っているのだろうか?」と。 <A>いかにもジミー・ブレズリンらしいコラムですね(笑)。 <M>確かにその要素はある。クリントンはモニカ・ルインスキーのために戦争を始めたわけではない。しかし、この戦いが終われば、誰一人、モニカ・ルインスキーのことを気にかけるものはない、ということを十分に認識していたことは確かだ。彼がどんなマイナーな罪を犯しても、市民は相互関係で判断する。戦争はルインスキーよりもっともっと大きな事件だからだ。一方、単純なことだが、彼は多くのアメリカ兵の犠牲を出すことができなかった。そんなことになったら、この国では大変な騒ぎになる。 <A>犠牲者が大量に出たら、反戦運動が全米に広がったかもしれないですね。 <M>あの戦争はやはりミステリーとしかいいようがないよ。西欧の各国でトップに上った者やNATOの首脳部と いうのは、全員キャリア組だ。トップに上る者に、聖者のような魂をもつ者なんているはずがない。なかには上り詰めるある段階で悪いことをしたかもしれないし、他の者は上り詰めるまでずっと悪事を働いたかもしれない。ところがいまや、全員がアルバニア人民に心を痛めるようになった。言葉もわからず、宗教も分かち合わないというのに、突然、ヒューマニストに変身した。あんなものはとても信用できない。 <A>グローバル・エコノミーのための西欧統合ということが主張されたわけですね。 <M>そう。だが、記憶の限り、何とも不体裁な戦争開始だった。ホルブルック(米特使)も、マデリン・オルブライト(米国務長官)も、誰もが警告されていた。あのミロシェビッチがいかに悪者か。もし空爆を開始すれば、彼は民族浄化を始めるぞ、と。 <A>だから、民族浄化は驚きでもなかったのですか? <M>彼ら、オルブライトとクリントンとNATOは、阿呆か悪魔かのどちらかだ。もし彼らが(空爆で)どれほど ひどいことが起こるかを知らなかったとしたら、彼らは馬鹿者だ。もし知っていたとしたら、彼らほどの悪魔もいない。実際に起ったことは、とてつもない動乱だったし、浪費だった。 <A>でも、空爆以外に方法がないとみんな思い込んだわけですね。 <M>僕の考えでは、「これがあなたの国の犯している犯罪行為だ。あなたは真実を報道されていない。国境に部隊を配備したから、3、4、5週間後には空爆するぞ」と書いたパンフレットをセルビア人に数週間撒くこともできたはずだ。そうすれば(空爆しかないということが)、もっとよく理解できた。ところがいまでは、腹立たしいことに、NATOは祝福を上げ、クリントンは「われわれは勝利した」などとのたまう。われわれは勝利などしてはいない。われわれは崩壊の淵に立たされているのだ。 <A>その通りですね。 <M>われわれは災難を引き起こして、その責任を取ろうともしていない。この先、破壊されたすべての建物を立て直すことになるだろう。でもそれはまるで、耳鼻科の医者のところへ行き、「鼻炎なのですが」と訴えると、その医師は鼻を切り取ってプラスティックの鼻を取り付け、「さあ、素晴らしい治療でしょう」というようなものだ。 <A>つまり、アルバニア人に対する虐殺やレイプを信じないという意味にとってよいのですか? <M>まあ、僕が信じるのは、バルカン半島に足を踏み入れることはいつでも災難を招くということさ。彼らは昨日ばかりでなく十年、百年、五百年、千年も憎しみ合っているんだからね。多分、もっとも複雑で苦悶に悩む土地なのだろう。だから、バルカンには簡単な解決法などない。解決することなどないのかもしれない。まあともかく、僕はこの戦争も、侵攻した理由も信用していない。戦う国家としての米国を考えてみると、ベトナムへ行ったときとは事情がまったく違っている。ベトナム戦争が終わったとき、アメリカ自身の概念の何かが変わってしまったのだ。 <A>ベトナムが米国をどう変えたというのですか? <M>われわれはもう決して、敢えてアメリカ人の血を流すことはしないと。僕自身の考えでは、もし、戦争へ行くのなら、少なくとも自国の血を流す覚悟が必要だ。 <A>その通りです。 <M>考えても見てごらん。1万5千フィート上空から爆弾を降下するんだ。(そんな上空では)一機も撃墜されるはずがない。まったくいまいましい。だが、僕には殺人についての考えがある。歳をとるに従って、人間の本性についてますます悲観的になってきた。人間というのは、全員、殺人者だと思う。つまり、われわれは自分自身のなかに殺人と自殺の要素をもっていると思う。でも市民化するにつれ、ほとんどの者はどちらの要素も表面に出てくることはない。それでも例えば、夫婦が50年も連れ添っていたら、すべてがよい結婚ではないにせよ、最後に先に死ぬ方はある意味で、もう一方に精神的に殺されたともいえるのだよ。 <A>そうですね(笑)。 <M>同じ日に一緒に死ねるカップルなんて稀だよ。 <A>そうしたくても、できるものではないでしょう。 <M>そういう意味ではなくて、殺人というものがわれわれのもつ要素のひとつだといいたいのだ。 <A>おっしゃることはわかります。 <M>僕らはかなりの程度まで人を愛することができるが、同じ程度で殺すこともできる。僕のいう殺人というのは、誰を殺しているかわからなければ、わからないほど、正当化できないということだ。 <A>なるほど。 <M>殺人はいつでも利己的行為だ。だが、ある殺人者は他の殺人者に比べて正当化できることもある。もし殺している相手を知っていれば、復讐の相手の顔をまじまじと見つめることもできるかもしれない。しかし、もし殺している相手を知らなかったら、もっと残虐な方法で殺すこともできるかもしれない。これではただの破壊行為だ。 <A>NATO軍がコソボを空爆していたとき、コロラド州リトルトンでふたりの生徒による高校乱射事件が起りま したね。たくさんの生徒が殺され、ひどいことだと大問題になったけれど、それならなぜ米国はコソボで空爆をしているのか?何とも皮肉でした。 <M>誰もあのふたつを結び付けることはできなかった。 <A>そんな声が上がらなかったので、ショックだったのです。 <M>アメリカには多くの知力があるが、誰もモラル上の道義心を求めようとしない。英国は19世紀に大きなパワーをもち、その期間中、彼ら自身の道義を探求しなかった。いま、アメリカが同じポジションにあるのだ。世界のなかの支配的国家になると、自国自身のモラルを追究しようとしない。 <A>ベトナムが米国をどう変えたというのですか? <M>われわれはもう決して、敢えてアメリカ人の血を流すことはしないと。僕自身の考えでは、もし、戦争へ行くのなら、少なくとも自国の血を流す覚悟が必要だ。 <A>米国はいつも戦う国家であり、いつも世界のナンバーワンになりたいと思うのでしょうか? <M>いや、その考えが広まったのは第2次世界大戦以降のことだと思うよ。20世紀の前半までの長いあいだ、ここが世界ナンバーワンの国という感じはなかった。しかし、世界最良の国という感じはあったね。他の国で差別されたり、協調できなかった者がここへやってきたのだから。もちろん、その意見にも単純化のきらいはある。確かに、西欧から来た者はアジアから来た者より親切にされたし、西欧から来た者は東欧から来た者より温かく迎えられた。とはいえ、そこには粗削りの真実が含まれている。米国に移民すれば、2世代、3世代目には裕福になれるということだよ。 <A>それはいまでも続いています。 <M>ところが、大恐慌が起こって、人々の信念は揺らいだ。第2次大戦後、その信念は持ち直し、ソ連と戦う道具の一部として広がり、われわれは地球上もっとも大切な国だという自信に変わった。それから50年、それはある意味で真実になったのかもしれない。生産的資源の豊かさと他国へ与える影響力のパワーという意味においてはね。われわれはその信念がすべてによいことなのか議論しようとしない。とにかく、われわれは盲目だからね。 <A>単純な愛国心溢れる人が多いですからね。 <M>われわれは繊細な国ではないし、国の大きさのわりに、愛国心を振りかざしすぎる。小国なら愛国心も構わない。必要だからね。貧しい家庭が「われわれにとって家族は大切だ」というようなものだ。しかし、金持ちはそんなことに構う必要がない。家族がそれぞれ勝手なことをしていられる。この国はこれだけ金持ちであるというのに、自国のことになるとすっかり敬虔になって、一本調子になってしまう。反米的なことをテレビで発言すると、もう出演依頼はこない。米国への批判や風刺は歓迎されない。というのは、心の奥底に不安が潜んでいるからだ。 <A>なぜでしょうか? <M>われわれの国は移民の国で、根無し草だからだよ。市民がアイデンティティ喪失を訴えることと同列の問題だ。特に中西部の者はアイデンティティ喪失を感じ、アメリカ人であることをやたら強調したがる。 <A>ニューヨーカーはあまりいいたがらないほうですね。 <M>東部と西部の住民は、自分が何者か、どこに属すのか、あまり探る必要がない。そればかりか、いまでは自分の生まれた街や育ったところを見つけられる人は稀なほうになってしまった。街や近隣、すべてが急激に変わってしまったため、ますます強く疎外されたように感じる。だから、より豊かで金持ちになったと思う一方、心のなかは不安定になってしまったのさ。 <A>この国に住んで、精神が不安定な人が多いのは驚きました。 <M>第2次大戦が終わったとき、アメリカ人は大恐慌が起こるだろうと思った。それにどう対処しようかと考えた。少ないお金でやりくりし、どうやって生計を立てるか心配した。しかし、実際にはまったく反対のことが起こった。'50年代の繁栄の始まりだった。人々は思っていたよりずっとたくさんのお金を手に入れ、そのお金をどうしたらよいかわからなくなった。金持ちになって不安になったのだ。そしていまでは、ほとんど気が狂わんほどの状態にある。あまりにも裕福で、毎日大金を使うこともできず、一生のうちに使い切ることもできない。これが大きな不安を呼んだ。だから、アメリカ人は、じっと座っていて、次の災難、その次の災難を案じる。だから、リトルトンの高校乱射事件に震え上がった。あれはどうみても理解を超えたことだった。そればかりか、災難を期待することにもなる。コンピューターのY2K問題ではすでに縮み上がっているみたいだね。 |
命を捧げたいと思えるほどの思想をもてない時代
| <A>『ノーマン・メイラーとの対話』という解説書で、編者のマイケル・レノンはこう書いています。「'60年代はメイラーにとって、もっともハッピーであり、騒がしくも、生産的な時代だった」と。この意見にはどう答えますか? <M>'60年代にわれわれはみんな、歴史を作っていると思ったものだ。もうあんなことは起こりえない。ちょうど、その年頃になる息子がいるからよくわかるが、いまの若い世代も同じ期待感をもっている。彼らは歴史という汽車に乗って、コンピューター・ランドに到着したようなものだ。しかし、彼らは歴史を作ることなど絶対にできない。'60年代にはわれわれの代表がすべてを本当に変革すると感じたものだ。確かにあの時代がいちばん興奮する時代だったね。 <A>振り返ると、いまでも'60年代は興奮する時代だったと思えますか? <M>振り返ってみれば、なんと愚かな時代だったことか(笑)。 <A>愚かな時代? <M>いや、愚かなんてことはない。僕らはベトナム戦争に反対した。あの戦争は反対するに値するものだった。あの戦争は不条理で、極悪非道、いまでも取り返しがつかないほどのものを残してしまった。ベトナムで培った悪い道義心はまだわれわれのなかに根づいている。 <A>その通りです。 <M>さっき僕が('60年代を)愚かな時代といったのは、われわれの楽観主義が愚かだったという意味だよ。われわれは揃って立ち向かった権威のパワーがどれほどのものか、理解しなかった。'60年代から現在を振り返ってみると、当時われわれが闘って勝ち取ろうとしたほとんどすべてのものが打ち壊されている。 <A>残念なことに、そうかもしれません。 <M>すべて反対の方向へ動いてしまった。われわれはアメリカに新しい価値観を求めた。われわれはたくさんのことを学ばなくてはならないという認識、われわれはすべてに解答を出せないという認識を求めた。ところがいまや、そんなことは忘却の彼方に追いやられ、アメリカはかつてなくパワフルだと自信をもっている。 <A>寂しいかぎりですね。 <M>もうひとつ'60年代に嫌悪したのは、プラスチックがどこにも氾濫するようになったことだ。われわれはプラスチックに圧倒されている。これが金属かプラスチックかもわらない(椅子をどんどん叩く)。こればっかりだ。何度もいっていることだが、プラスチックというのは石油の排泄物さ。きっとどこかの悪魔のような天才がこういったに違いない。「見たまえ!われわれは大金を垂れ流している。この石油の“クソ”から何か作れるに違いない。これこそ捜し求めていた金の卵だ」と。そこでプラスチックは生活の隅々にまで忍び込んだ。たぶん、いまでは石油産業より繁盛しているに違いないね。 <A>そういえば、そうですね。 <M>赤ん坊が初めて口に入れるものはプラスチックのおしゃぶりだ。そしてプラスチックの椅子。いまの子供たちが何ものにも深くコミットできないというのは、プラスチックのせいだと思う。(ほんものに触れなかったために)無感覚になってしまったからだ。 <A>'82年、『ニューヨーク・タイムズ』紙へのインタビューで、「'70年代の特徴は、誰もが命を捧げたいと思えるほどの理想をもてなくなった時代」と答えています。20世紀最後の現在も同様でしょうか? <M>もちろんだ。何かの理想のために死ぬなんて奴はもういないよ。いまでは、理想のために死ぬなんて奴は狂人だけだ。 <A>狂人? <M>狂人、正気を失った人。あのリトルトンの高校乱射事件で多くの生徒を撃ち殺したふたりの少年は、理想のために喜んで命を捧げた。彼らの理想とは何だったのか?自分たちが重要な人物であることさ。そればかりか他の生徒の恐怖に歪んだ顔を見たかったのだ。 <A>あれが理想ですか?あまりにも狂っていた。 <M>まあ、あれも理想だよ。「自分たちは重要」という理想だ。その理想のために命を捧げたのさ。コソボに話を戻すと、あの戦争の(本質を理解する)カギは、誰も死んでいないということだ。向こう側でどれだけ死者が出たかは別にして、アメリカ人はあの戦争で死ぬべきでないということだ。この国には命を捧げるほどの理想がない。命を捧げるほどの理想をもたない国は、戦争に出かけるべきでない。その後に平和など訪れるはずがないからだ。もし双方が命を捧げるほどの理想のために戦ったら、それはおぞましい血みどろの戦いになるだろう。もし、理想 がパワフルであればあるほど、ひどいことになる。だが、戦争が終われば、ああひどい戦争だった、何という悲惨 か、と振り返って、何らかの修復が行われる。それに50年もかかるかもしれない。それでも修復できないかもしれない。しかし、あまりにも双方の犠牲が大きいので、あれは悪夢だったという歩み寄りが生まれる。ところが、もし一方が理想なく戦ったとしたら、彼らは死刑執行人と同列になってしまう。 <A>死刑執行人? <M>もし、戦う理想もなく戦争をしたら、(その国の軍隊は)死刑執行人だ。命を捧げるほどの理想をもてないことが、いまという時代のいちばんの難しさだと思う。誰も理想のために死のうとはしない。 |
中流階級にひそむ危険
| <A>レーガンの時代は、'60年代とベトナム戦争の傷を癒そうと努めた時代だったように思えますが、アメリカ人は彼の考えに操られたと思いますか? <M>その通り。レーガンはハーメルンの笛吹きだった。いま振り返ってみても、彼はしごく単純で抜け目がなかった。彼はたったひとつの政治的理想しかもっていなかった。アメリカ人は信じられないほど馬鹿で、途方もないほど愛国的だと。彼はたぶん歴代もっとも恥知らずの大統領だろう。たとえば、彼のグラナダ侵攻。なぜあそこへ攻め込んだのか?というのは、まったく馬鹿馬鹿しい理由で273人の――人数はともかく――海兵隊員がレバノンで殺されたからだ。5日後、あるいは3日後にグラナダへ侵攻した。なぜか?この国に対する共産主義の深刻な脅威に対処するためだといって、1800人ほどの海兵隊員を送り込んだ。キューバ兵がいるからというのが理由だ った。しかし、実際そこにいたのは1200人くらいのキューバ人建設労働者だった。われわれは1日か半日ほどで勝利した。そこでレーガンは「いまや、われわれはベトナムの痛みと傷から回復したのだ」というような発言した。それからブッシュの戦争。僕はブッシュの湾岸戦争と呼ぶんだが、あれはもっと危険だった。ブッシュは出たとこ勝負だった。あれは保障された戦いではなかった。サダム・フセインが「これはすべての戦争の源になる」といったのをおぼえているかい。ブッシュはきっと眠れない夜を過ごしたに違いない。もちろん、ブッシュはアメリカ人の犠牲を最小限にとどめて、あの戦争を終わらせようと必死だった。だから3日早く終結させてしまい、結局われわれはその対価を永遠に支払うことになったのだ。 <A>21世紀について伺いたいのですが、コロラドの高校乱射事件の話が何回か出ています。あの世代の若者たちについて不安を感じますか? <M>もちろんだ。彼らはどうしてよいかわからないからだ。僕のいちばん下の息子で21歳になるジョンは、彼らの世代には友情以外に何もないといって不平をこぼしている。唯一、彼らのあいだで起こっている運動は、ポリティカル・コレクトネスだけというのだ。大学ではすっかり盛んらしいね。しかし、ポリティカル・コレクトネスでは何も解決できない。感情を抑えることができないからだ。しかし、それがポリティカル・コレクトネスの意図する ところだ。「こういうふうに感じなければならない」と命令する。日本人は僕よりよくわかるだろう。このように感じ、考え、過ごせと強要される罠に陥ると思う。 <A>日本では神戸の郊外にあるモダンな新興住宅地で14歳の少年が5歳の少年を残虐に殺害する事件が2年ほど 前に起こりました。いまでも衝撃は消えないほどですが、急増する少年犯罪を考える時、われわれは若い世代より社会に責任があると考えるべきですか? <M>いつでも誰かに責任を擦りつけることはできる。1カ月ほど前、郊外に住む友人を訪ねたんだ。招いてくれたのはなかなかいい夫婦でね。向こうの奥さんとうちのが友達で、一緒に一日を過ごした。それで、一日何をしていたかというとテレビを見ているだけ。話をするより楽だからね。外に出てみると、郊外の街だった。知り合いの家はいい感じに家具調度も揃っていて、その隣のうちも同じようなセンスで同じように飾られているのだろう。しかし、隣とは何の付き合いもない。さらに、道路も本当の道と呼べるものではない。歩いてみようとしたが、すぐ飽きてしまった。何もなくて、偶然何かが起こることがない。すべてが計算し尽くされているからね。まるで死んだ ようなところだったよ。そこで僕はこう思った。ここではきっとひどいことが起こるに違いない。何もひどいこと が起こっていないから。 <A>ニューヨークとは正反対ですね。 <M>そう、僕はよくいうんだ。ニューヨークの住民は誰よりもハッピーだと。住民は議論がましく、いらいらすることばっかり。多少の危険があるから、生き生きしていられる。 <A>(笑)本当。米国の学校乱射事件は必ずといってよいほど郊外で起きていますね。 <M>古くからの郊外ではなく、新興の郊外だ。古くからある郊外は、2世代、3世代が住んできた街になっているから、ちょっとした歴史がある。さっきの言葉をもう一度使えば、根があるんだ。ところが、新しい郊外というのは不動産業界の凡庸な人物によってデザインされたもので、どんなことがあっても住みたいと思わせるものではない。 <A>でも、多くの人々が新興住宅地の新しい一軒家に住みたいと思っていますよ。そこで中流の暮らしを楽しみたいと。 <M>そう、中流階級というのは危険な階級だ。というのも、人々が中流階級になりたいと思うのは、一般的にあまり心配がないからだ。労働者階級では、往々にして親父がのんべえだったり、母親は働き過ぎで機嫌が悪いなんてものだ。あるいは、悲惨な家庭状況だったりね。子供は貧しい環境で育つから、タフにならなくちゃならない。 <A>ボクシングの選手になったり、マフィアの一員になったりする子も出てくるわけですね。 <M>労働者階級の出身ならば、15歳までには生き延びる術を身につけているだろう。ところが中流階級は、全体のコンセプトが人生保護にある。中流階級は保護されている。そこで中流階級になると、危険のないところを選んで住む。それが次の危険を呼んでしまう。誰も身を守る術を知らないからさ。英語には“ストリート・スマート”という表現があるくらいだ。さて、中流階級の子供が名のある私立大学などへ行って、ストリート・スマートのセンスがないまま、政府の要人になったりする。クリントン政権のトップに立つ何千人かのほとんどが新しい郊外で育ち、いい大学へ行ったんじゃないだろうか?そして、ストリート・スマートはますますいなくなる。 <A>恐ろしいことですね。 <M>ガッツのある賢者など出てくるはずがない。マデリン・オルブライトのような人物対ミロシェビッチのような人物という構図を考えてみるといい。ミロシェビッチは人類が想像もできないほどの汚いトリックを知っている奴だ。そのうえにはそのうえの、もっと老獪なのがいる。あのロシア人たちこそはもっと汚いトリックを知っているのだ。そんな(中流階級の)人生を送ってきた者のなかに、ミロシェビッチと交渉できる者などいるはずがない。 |
ヘミングウェイは、叔父か父親代わりのような存在
|
●
|
 |
|
●
|
|
<A>文学について伺いたいのですが、いまの若い人たちは本を読みません。特に文学をね。なぜそんなことになったのか?彼らは文学と自分自身をつなぎ止めるものを見出せないのか、あるいは文学が本という形で、彼らの心に届かないのでしょうか? |
今世紀もっとも成功した革命は女性解放運動
|
<A>質問しずらいことですが、死について考えますか? |
| ノーマン・メイラー/1923年、ニュージャージー州で生まれ、ニューヨークのブルックリンで育つ。 ハーバード大卒、仏ソルボンヌ大・大学院卒。第2次世界大戦の従軍体験をもとに、'48年に『裸者と死者』を発表。'68年、『夜の軍隊』で全米図書賞、ピュリツァー賞を受賞。'80年には『死刑執行人の歌』で2度目のピュリツァー賞。その一方で、スキャンダラスな話題にも事欠かない。とくに'60年、 夫人を刺して瀕死の重傷を負わせた事件は世間を驚かせた。ベトナム反戦デモで逮捕されたり、 '69年にはニューヨーク市長選に立候補して落選したりと、書斎派というより、常に行動する作家であった。その他の主な著書に、『鹿の庭』('57)、『ぼく自身のための広告』('59)、『アメリ カの夢』('65)、『性の囚人』('71)、『マリリン』('73)、『ザ・ファイト』('75)、『天才と欲望』('76)など。 |
| 青木冨貴子(あおき・ふきこ)/1948年、東京都生まれ。 『ライカでグッドバイ――カメラマン沢田教一が撃たれた日』で注目され、以後『アメリカを探せ』『たまらなく日本人』『星条旗のアメリカ』『ジャーナリスティック・アメリカ』(以上、文藝春秋)『ニューヨーカーズ』『デンバーの蒼い闇――日本人留学生はなぜ襲われたか』『ガボものがたり――ハミル家の愛犬日記』(以上新潮社)、『「風と共に去りぬ」のアメリカ――南部と人種問題』(岩波新書)など綿密な取材に基づく作品を発表。'84年か ら3年間『ニューズウイーク日本版』支局長を務め、'87年作家のピート・ハミルと結婚。ニューヨーク在住。 |
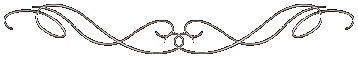
![]()
Copyright(C)2003 SHUEISHA CO.,LTD. All rights reserved.