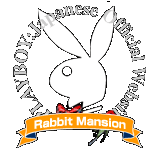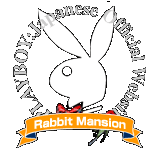
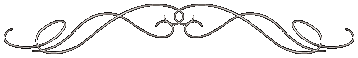
-PBインタビュー・コレクション-
石原 慎太郎
「人生は平凡でいいと安く括る奴は、しょせんそれだけの男にすぎない」
高橋昇=写真
| 都知事選に圧勝した男は、たえず挑発的で、好んで物議をかもしているふうに見える。が、つねに時代の寵児でありつづけるダンディは、自らの感性に率直であることに最高の価値を置くがゆえ、内なる規範に忠実であるがために、常識の枠を突き抜けてしまうだけだ。PLAYBOY
INTERVIEWの再開を祝し、日本で一番アクチュアルな男に、その男性哲学を、石原慎太郎という生き方を問うてみた。 |
|
●
|
|
|
|
●
|
| 6月の日ざしがまぶしい午後。三島由紀夫に話題がおよんだあたりだったと思う。石原慎太郎新都知事の躍動的な語りの起伏に耳をすましていると、執務室の空気がややざわめいた。けげんな顔で石原が問いかけると、どうやら贈られた花とともに運ばれたカマキリの卵が陽気につられて孵化し、小さくともすでに険しい前肢で獲物を狙いすます兵士たちが、そこかしこの壁で散歩としゃれこんでいるではないか。石原は破顔一笑。カマキリの名はギリシャ語の予言者に由来し、アフリカの神話ではしばしばトリックスターになぞられていたはずだ。取材者一
同はこの偶然を喜び、いかにも価値紊乱者のインタビューに相応しい、と囁きあった。 |
|
<PLAYBOY(以下PB)>今回はダンディズムについて伺いたいのです
が、ずばり、あなたにとって、人間が一番エロティックに見える瞬間とは何でしょう?
<石原>月刊PLAYBOYはずいぶんむずかしいことを聞くんだな。弱ったね、そんな高級なことに答えなきゃないけないのか(笑)。エロスとエロティックは違うし、僕の場合、自らの感性を率直に発揮して、物を言ったりする瞬間かな。それも芸術作品より、その人間の肉体的な表現の中で、感性に則って現れてくるものにエロスの輝きを感じるね。存在感というのかな。僕が若造だったせいか、かつての先輩には皆、大なり小なり魅力があったもんですよ。それが、その人間の持
っているエロスということでしょう。
<PB>35歳前後がわれわれの読者のメイン・ターゲットになるんですが、'68年
に参議院全国区選で至上最高の得票でトップ当選されたのが35歳の時でした。その目で御覧になって、今の35歳に一番欠けているものは何だと思われますか。
<石原>そんなものは自分で見つけて、いったい何が足りないのか考えればいいんで、人にどうこういわれて気づくもんじゃないさ。世の中には今もすぐれた人間
はたくさんいるし、自分の能力を発見し、開発するのは自分自身でしかないんだから。結局、自分の人生は平凡でいいんだと安く括っちゃう奴はダメだし、ダメだから人に安易にすがろうとするんだろうな。
<PB>そのくせ、家族は幻想だとか、自分一人で生きていける風の錯覚が罷り通
っています。
<石原>死ぬときは一人とはいえ、人間は一人では生きていけないし、生まれてもこれないわけですよ。人間は様々なことを執着して考えるけど、僕の場合、「存在」というものに一番興味があって、存在の問題をつきつめていくと、結局は肉身や先祖について考えざるをえない。他者あっての自分、自分あっての他者であり、かつ自分と他者との関係を深く考えるなら、自分が核になるほかない。それがまさしく実存ということです。存在について語っていたら、とてもダンディズ
ムの話に行き着かないよ(笑)。「性と死の対置」は僕の文学の主題ですから。 しかし、肉身の絆が希薄になっていくっていうのは何だろう。では、ほかに頼れるもの、確かなものがあるのかね。一番身近な他者は兄弟であり、肉身でしょ。
そのかかわりをネグってしまったら、人生も成り立たないし、人間そのものも成り立たないんじゃないか。僕は自分に興味があって、威張っている人にさえ絶えざる関心があるんだけど、アパシーというか、無関心さ、ノンシャランス、肝心
なことについてだけは自分で考えない体たらくね、これは堕落以外の何ものでも ないでしょう。退屈していれば他人に関心を持つはずなのに、現状に十分満足しているのかね。
<PB>あらゆることを疑ってかかったり、物の味方の遠近法を自ら調整して物事を見つめることをさぼってきたような気がします。
<石原>あてがいぶちに甘んじているんだろうな。氾濫する情報が、かえって人間の想像力を疎外し、肉体の自覚すら奪ってしまう光景に肌寒い思いがするね。あちこちに書きましたが、物がないという飢餓感美しいし、それ自体満ち足りたも
のです。いつも満腹すると、人は幼稚になる。
<PB>男が最後に守らなければいけないものは何だとお考えですか。
<石原>何をもって男のマチズモとするかは人によって違うだろうから、一般論では語れないな。僕はかなり風変わりらしいから(笑)。ただ、自分の感性には率直でありたい。言い換えるなら、自由でありたいよね。感性を信じなかったら、人間が生きていく意味がない。僕は、小林秀雄という人が好きだったんです。それと、彼を男として愛し評価した白州次郎みたいな男。歯に衣着せぬ、とはちょっと違って、やっぱり率直で、自分の感性をむき出しに生きた男たち。ダンディでしたよ。こんな生き方をしたいと思いながら見てましたね。
<PB>『国家なる幻影−わが政治への反回想録』を読むと、ベトナム戦争の取材ののちに大病を得、いたたまれなくなっていたときに三島由起夫さんから一つの手紙をもらい、「私を政治に向かって導いていったもの、というよりその水口を開いてくれたのはあの手紙だったともいえる」とお書きになっていますね。また
別に壱章を三島さんの自決に割き、いたるところで三島さんが生きていたらどう考えるだろうと自問されています。
<石原>あの人は非常に頭のいい人だったけど、三島さんその人にはエロスはなか
ったな。エロスに憧れていたが、ついにエロスを持てなかった人だと思います。 20台の終わりの頃かに、三島と話していて、川端康成さんのどの作品が一番好きか尋ねられてね。僕が『みずうみ』といったら、あんな不定型でドロドロした、破綻した作品はダメだと言下に否定された。破綻しているからこそいいんじゃないないんですか、破綻しているからこそアヴァンギャルドじゃないですか、って反発しても、破綻を破綻で書いても芸がないと、決して譲らなかった。僕は逗子で緒、しばらくして、鎌倉に住んでいた川端さんと電車で一緒になって、今度は僕が川端さんに、自作で一番好きなのは何か、聞く機会があったんです。すると、お読みになったかどうかは知りませんが、最近書いた『みずうみ』が好きで
す、とおっしゃる。僕は呵々大笑してね、いや三島さんにそう言ったら怒られましたと。すると川端さんがあの目を爛々と光らせ、しかし静かに笑いながら、あれは三島君には絶対にダメでしょうと言うんです。そのときの川端のすごさね。作家として、男として、実にセンシャルな存在感でもって、三島さんをばっさり斬るわけでしょ。そういうときの川端さんの魅力、エロスが忘れがたくあるよ
ね。三島さんの感性もだんだん変質し、社会的事件におんぶして、物を書くようになり、晩年に評価された小説が『宴のあと』や『絹と明察』になっちゃうんだ
ね・・・。自らを観念で構築していった先がボディビルになってしまう。破綻のない肉体じゃ動けないし、塑像みたいにただ立っている文には壊れずん済む。観念だけでは把握しえぬもの、例えば輪廻転生を機軸に据えた最後の『豊饒の海』
なんて、見るも無惨なほど薄っぺらいし、自己模倣に終始しています。僕はあれをとても読めなくて、1週間ほど怪我して謹慎していたときに読んだんですよ。僕は三島さんが好きでしたから、かわいそうで涙が出ました。ここで三島論をやる気はさらさらないけれど、でもやっぱり頭のいい人で、面白かったよ。三島由紀夫のいない日本は本当につまらなくなったし、僕がいなくなったら、もっと日本はつまらなくなると自惚れていますけれど(笑)。
|
Back to top▲
|
●
|
|
|
|
●
|
|
<PB>ご自分にとってのアメリカを簡潔に定義していただけますか。
<石原>アメリカは、僕の下意識に重く影をひいてあるんです。永遠の主題の一つはアメリカかも知れな
い。それは、戦争を体験しているからです。いろいろな人間が死んでいくのをまざまざと見せつけられたからね。今の北朝鮮みたいに、天皇を神と信じ、ウルトラ・ナショナリズムに引きずりまわされるがままの時代に、逗子はハイカラでしたから、部屋を閉め切ってジャズを聞かせてくれる先輩なんかもいる。機銃掃射を仕掛けてくる艦載機の機体にミッキーマウスの絵がハッキリ見える。そういう鮮烈な異文化体験だったわけです。戦場に行きそびれた遅れてきた少年の眼で見ているから、そこでの刷り込み、プリン手ぃん具は大きい。つっぱってたんで、アメリカ兵に殴られたこともあったし、アメリカに対する感情は複雑だね。
<PB>『国家なる幻影』でもとりわけ印象に残るのが、アメリカへのアンビヴァレントな感情でした。戦後日本を解体し尽くしたアメリカがあり、一方国益の徹底的な追求に羨望を隠してはおられない。
<石原>あの本でも書いたかな。『「NO」と言える日本』のアメリカ版キャンペーンのさなかに、有名な日本バッシャー、民主党院内総務のゲッパードと話す機会があってね。
<PB>ゲッパードが、アメリカと日本は夫婦みたいに切っても切れない、と言う。石原さんがすかさず、どっちが夫で、どっちが女房かを問い詰める。返答に窮していると、追い討ちをかけるように、日本が女房でもいいが、情婦じゃないぞ(笑)。
<石原>それで、お前が変わった奴だが、面白いなんてことになってさ。すっかり打ち解けたとき、ゲッパードが、アメリカに対する君の基本的なメンタリティは何だと聞くから、ホスティリティ、敵意と答えてやった(笑)。米兵に殴られた逸話を持ち出すと、お前を殴ったのは黒人だろう、と。違う、白人二人だったと答えたら、絶句していたけどね(笑)。戦後に関する分析で、事態を正確にとらえ、深い部分にまで立ち入り、文明批判、日本批判にまでなりおおせているのは江藤淳の仕事ぐらいなものですが、江藤が『アメリカと私』を書いたときも、なんでこんな物を書くのだとアメリカ側から違和感が表明され、江藤自身、心外と書いていたけれど、アメリカ人の驕り、自惚れにかまけていられないという気持ちもたしかにあるんです。が、それはそれで敗戦したから仕方がないという気もするんだな。たとえると、最近はもうタフじゃないからあまりやらないんですが、テニスのシングルス。子供相手に負けたのならいざ知らず、こいつには勝てると思って臨んだ試合で大敗すると、これがきついんだよ。ダブルスと違って、シングルスで負けると、次の日コートで相手に会っても嫌な気分になる。こいつにはかなわんと思ったら、そいつとはできるだけやらないようにするしかない。
悔しさ、口惜しさ、憤りが堆積したコンプレックスは本当に厄介です。
<PB>『国家なる幻影』の通奏低音に、「死」の問題がありますね。かたわらをあまたの死が通過し、政治家という屍を累々と築きながら、あとから来る者がそれを踏み越え、成就するのが政治なのだと。
<石原>それは政治の世界に限ったことではないが、特に政治家は大方不本意な死に方をしているからね。また、その方が政治家らしい死に方とも言える。うちは武田の士族の出でね。家訓が“明日の戦、我が身は無念と心得うべし”っていうんです。とても虚無的だけで、しかし覚悟が決まっていて、なかなかいい言葉ですよ。死を意識するとは、ぎりぎり生きること。それがダンディズムの条件でしょうな。小林秀雄なんてじつに爽やかで、最高の感性、教養があってね。まあ小林さんのフランス語はいい加減で、今(日出海)さんがずいぶん手を入れたらし
いけどな(笑)。小林さん、白洲さん、僕ら兄弟が親代りにしていた水野成夫、東急の総帥・五島昇・・・自分の感性を信じ、感性に忠実で、男ぶりがいいダンディでしたよ。本来は芸術家こそが自由で、我を隠さず、まわりをちっとも気にせず、傍若無人でいいはずなのに、近頃の芸術家は皆サラリーマンになっちゃって、つまらないんだよ。こちらが見巧者になったせいか、こっちが年を取って、皆、若けえなという気がしてならないんだけど、過去にいくばくかダンディたちと出会えたことは楽しかったし、これに勝る人生の幸せはないな。特に人生の最
初の頃、本当にいい男たちとすれ違えたと思う。その点、えてして政治家はダメ だなあ。構えすぎてるんだな。中学生の頃か、石原、一番明るい色は何だと、教師に言われたもんだから、黒です、って答えたら、アカデミックな教師にふざけるなってとことん叱られてね。でも、僕には黒は鮮烈だったがために明るくみえただけです。昔から、常識で一律化するのはつまらんと思っていたし、常識では律しえないものがあるのもわかっていたし、自分の内なる規範を曲げる気はなかったし、それで政治家としての成功がむずかしいんだろうね。
<PB>戦後にはびこる平凡至上主義を早くも憎悪されていた(笑)。ところで、フィクションの中で男を感じる人物といったら?
<石原>アンドレ・マルローの『王道』の主人公、ペルカンなんていいじゃないで
すか。ジャングルの中で死んでいくとき、女との束の間の恍惚ののち“死、死な どありはしない、ただこの俺だけが死んでいくのだ”と。官能的で、死ぬ寸前まで女を抱いて、男の死の行為を言いつくす言葉を吐く。もっと下世話に言うと、そりゃ『モンテ・クリスト伯』でしょう(笑)。引き裂かれた愛を踏まえて、巨万の富を得、数十歳年下の王女を彼女にしてだな、復讐を遂げ、最後は希望という名の船に乗って水平線に旅立っていく。いいじゃないですか。ああいうぬけぬけとした主人公、このころは誰も書けなくなっちゃったな。総じてロマネスクがありえなくなったからね。でもこの間、マロリーの死体が発見されたでしょう。あれは非常に感動したな。
<PB>ヒラリー以前にエベレストを征服していたかもしれない英国人。
<石原>写真一枚見つかるなり、カメラが発見され、登頂したという証拠が出てきてほしかった。でも死んでから数十年の沈黙が破られたには違いないな。それが人生ってもののロマンだよね。
<PB>あなたにとって、最後に残るものは?
<石原>やっぱり言葉でしょうね。イデーと感性が重なりあって収斂し、醸造されて出てくるのが言葉。そこにしか本当の価値はないものな。早稲田の大隈重信と慶応の福沢諭吉に変な対比があってね。大熊は有名な政治家になったけれど、今では福沢の方が圧倒的な存在感があるでしょう。それは、大熊が言葉を残さず、福沢が言葉を残したからですよ。最後に残るのは、本当の言葉しかない。
<PB>デビュー作の『太陽の季節』にはハードボイルドの萌芽を見る向きもあって、つねに異端児視されていたようにも見えますが、ご自身は日本文学から切れているとお考えですか。
<石原>それぞれの作家が自分は孤立していると主張し、日本文学に連なっていないつもりでも、実はつながっているし、日本語で書く以上、そうでない作家はありえないでしょう。僕は古典に精通しているわけではないけれど、例えば永福門院の歌がとても好きで、ヨットで仲間が寝ていて一人舵をとりながら、暮れていく海、明けていく海を眺めていると、彼女の歌をふと思い出し、自分と同質の何かを感じたりしますよ。結局のところ、僕らは風土とその情感からは逃れられないんじゃないかな。最近思うのは、入江隆則が指摘した日本人の融通無碍なる価値観、ここに世界に希望を与える可能性があるんじゃないかということです。裁く神、絶対神でなく、多神教に、です。イスラム原理主義者とキリスト教の血なまぐさい対立を見るにつけ、宗教とはいったい何だったのか、考えざるをえません。
|
| 花の上にしばしうつろふ夕づく日入るともなしかげ消えにけり。常 はよりもあれなりしを限りにてこの世ながらはげにさてぞかし。いずれも鎌倉時代の女流歌人、永福門院の手になるものだ。石原の口から古典への親炙を聞くのは意外にして喜ばしい発見だったが、そういえば石原が愛するダンディ、ケンブリッジに学び、帰国語はベントレ−を駆って吉田茂のブレーンとなり、GHQに啖呵を切った白洲次郎について白洲正子夫人が記したことを想起していた。氏は今どき珍しい直情一徹な士であったが、しょせんは平和な世の中に通用する人間でなく、性格的にも乱世に生きがいを感じる野人であった、と。話に釣り込まれて時間を忘れていた。そろそろ席を立とう。すると、それを制して言う。 |
| <石原>伊藤整が昔、僕に言ってくれたんだ、あなたは今一番いい時期ですってね。当時は若くてもっと飛んだり跳ねたりしていてさ。文学以外に何か好きなことをやったらいい、って。訳を聞くと、あなたは作家だから何でも許されるし、失敗したら、それを書けばいいんです(笑)と。こんな人を喰った話はないんだけど、シニックでいて、暗示的で、いまでも僕はそれを信じていますよ。今も東京を恋人にした大恋愛小説を書くつもりでやっているし、冒険心と好奇心は同義語なんだから、男たちよ、平凡に甘んじるなという結論だね。 |
Back to top▲
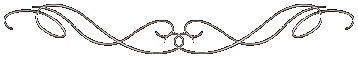

Copyright(C)2003 SHUEISHA CO.,LTD. All
rights reserved.
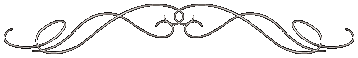


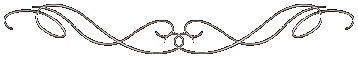
![]()